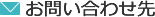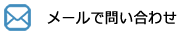不活化ポリオ予防接種
更新日:2023年4月1日
ポリオ(急性灰白髄炎)とは
ポリオ(急性灰白髄炎)は、「小児まひ」と呼ばれ、日本でも1960年代前半までは大流行を繰り返していました。口から入ったポリオウイルスは咽頭や小腸の細胞で増殖します。小腸の細胞ではウイルスは4日から35日間(平均7日から14日間)増殖すると言われています。増殖したウイルスは便中に排出され、再び人の口に入り抵抗力(免疫)を持っていない人の腸内で増殖し、人から人へ感染します。
ポリオウイルスに感染してもほとんどの場合は症状が出ず、一生抵抗力(終生免疫)が得られます。症状が出る場合、ウイルスの感染で血液を介して脳・脊髄へ広まり、麻痺をおこすことがあります。ポリオウイルスに感染すると100人中5人から10人は、かぜ様の症状があり、発熱を認め、続いて頭痛、嘔吐があらわれます。
また、感染した人の中で、約1,000人から2,000人に1人の割合で手足の麻痺を起こします。一部の人には、その麻痺が一生残ります。麻痺症状が進行し、呼吸困難により死亡することもあります。
ポリオワクチンについて
ポリオの予防のためにこれまでは口から飲む生ポリオワクチンを使用してきましたが、ワクチンに使用されているウイルスが脳脊髄に達して、まれに手や足に麻痺があらわれたり、予防接種を受けた人から周囲の人に感染する可能性もありました。
厚生労働省は皮下注射の不活化ポリオワクチンを承認し、平成24年9月1日より単独不活化ポリオワクチンの予防接種が開始されました。不活化ポリオワクチンは不活化した(殺した)ウイルスから免疫をつくるのに必要な成分を取り出して、病原性を失くして作ったものです。生ポリオワクチンとは違い、麻痺の心配はありませんが、他の皮下注射と同じような副反応(発熱・疼痛・紅斑など)が起こることがあります。
平成24年11月より不活化ポリオワクチンと三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)を合わせた「四種混合ワクチン」が開始されました。不活化ポリオワクチンと三種混合ワクチンの接種回数が同じであれば、四種混合ワクチンへの移行ができます。
対象年齢と接種回数・間隔
生後2か月から90か月未満(7歳半の誕生日の前日まで)
【標準接種年齢】
- 初回接種:生後2か月から12か月の間に20日以上の間隔をあけて 3回
(20日から56日の間隔が望ましい) - 追加接種:初回接種終了から12から18か月の間隔をあけて 1回
(6か月以上あければ接種可能)合計 4回接種
海外などで生ポリオワクチンや不活化ポリオワクチンを途中まで接種されたかた
標準接種期間を過ぎても90か月未満(7歳半の誕生日の前日まで)であれば公費で接種ができます。下記に記載するパターンを参考に、生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンを合わせて合計4回となるよう残りの回数を接種してください。
- ポリオワクチンをまだ1回も受けていない
不活化ポリオワクチンを合計4回受けてください。
不活化ポリオワクチンは、初回接種3回+追加接種1回の合計4回の接種が必要です。 - 生ポリオワクチンをすでに1回受けている
不活化ポリオワクチンをあと3回受けてください。
不活化ポリオワクチンを、初回接種2回+追加接種1回の合計3回の接種がさらに必要です。 - 不活化ポリオワクチンを1から3回受けている
不活化ポリオワクチンが合計4回となるよう残りの回数を受けてください。 - 生ポリオワクチンをすでに2回受けている
不活化ポリオワクチンの接種は必要ありません。
生ポリオワクチンをすでに2回接種完了されたかたは、不活化ポリオワクチンを接種する必要はありません。
予診票について
これまで配布していた生ポリオワクチンの予診票は使用できません。
不活化ポリオワクチン用の予診票は、あいぽっくか市内指定医療機関に用意してあります。
注意:不活化ワクチン用の予診票には 「これまでに[生]か[不活化]のポリオ予防接種を受けたことがあるか?ないか?」の質問の欄があります。 必ず、それまでに受けた回数を○で囲んでお答えください。
指定医療機関
子どもの予防接種と市内指定医療機関をご確認ください。- 立川市・小平市・小金井市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・武蔵村山市の指定医療機関は、乗り入れを行っております。この場合は予診票は昭島市のものを持参してください。予診票は母子健康手帳を持ってあいぽっくへ直接取りに来ていただくか、電話で請求していただければ後日郵送することも可能です。
保健福祉部 健康課 健康係
郵便番号:196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130