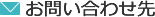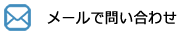離乳食よくある質問
更新日:2025年4月2日
離乳食に関するよくある質問をまとめています。
食事は個人差があるので子どもによって悩みも様々です。日ごろから子どもの様子をよく見ていくことが大切です。
「離乳食講座」や「乳幼児食事個別相談」も行っていますので、ぜひご参加ください。
離乳食開始前
なぜ離乳食が必要ですか?
回答
体が大きくなり動きも活発になってくると水分の多い乳だけでは必要なエネルギーや栄養が十分に」とれません。そのため、食物から栄養をとる必要がでてくるので、固形物を食べる練習が必要になってきます。
離乳食開始前に準備することはありますか?
回答
授乳するタイミングを規則的にして、離乳食を食べるタイミングでおなかが空くように、赤ちゃんの生活リズムを作っておくとよいです。
初期(生後5から6か月ごろ)
食べさせても口から出してしまいます
回答
離乳食を始めたばかりのころは、哺乳の反射が残っている場合があり、口から押し出してしまうこともあります。必要な栄養の大半を母乳やミルクで摂っている時期なので、量をたくさん食べさせることよりも、食べ物やスプーンに慣れることを大切にして食べることを続けていきましょう。
離乳食を嫌がりなかなか食べてくれません
回答
赤ちゃんが離乳食を嫌がる理由は「味、形状、温度」や「スプーンの感触がいや」「周囲がにぎやかで気になる」などいろいろ考えられます。
また、おなかが減りすぎているとゆっくり離乳食を食べることがもどかしくなり、慣れていてごくごく飲めるミルクや母乳を欲しがります。このようなときは、離乳食の時間を30分くらい早めて、おなかが空きすぎないうちに食べさせてあげてください。
食べたものがウンチにそのまま出てきます
回答
食べたものがそのまま出てくるのは、消化の練習中です。特に、にんじんやほうれん草など色鮮やかなものは目立つので気になりますが、赤ちゃんの機嫌がよく、下痢をしていなければ心配いりません。離乳食を始めた頃は便がゆるくなったり、便の回数が1-2回増えることがあります。
離乳食を始めてから便秘になってしまいました
回答
離乳食は、おっぱいやミルクに比べて水分量が少なく、便が硬くなりやすいです。また、消化吸収の練習中のため便の調子が整わないこともあります。赤ちゃんの機嫌がよいようなら「水分をしっかり取る」「野菜量を増やす」「腹ばいやハイハイなど腹筋を使う動きを増やす」「ヨーグルトなどのビフィズス菌をとる」ことを意識してみましょう。
もし、便秘で具合が悪いかなとおもったらかかりつけの小児科を受診しましょう。
アレルギーが心配です
回答
離乳食の開始や特定の食物の食べ始めを遅らせても、食物アレルギーを予防できる根拠はありません。初めて食べる食材は1日に1種類までにして離乳食用のスプーンひとさじくらいから食べ始めましょう。すすめていくうちに、食物アレルギーを疑われるような症状が見られたときは、自己判断をせずに、必ず医師の診断に基づいて対応しましょう。
注意特定の食品を除いた「除去食」は医師の指導のもとおこなってください。
卵を食べさせることが心配です
回答
卵の摂取開始を遅らせないことが卵アレルギー予防の効果があることがわかっています。離乳食を始めて3週間ほどして魚や豆腐などたんぱく質を食べることに慣れてきたら、しっかり火を通した卵黄を少量から始めましょう。すすめていくうちに、食物アレルギーを疑われるような症状が見られたときは、自己判断をせず必ず医師の診断に基づいて対応しましょう。
2回食にすすめるタイミングは?
回答
「離乳食をスタートして1ヶ月以上過ぎた。」「口唇を閉じて上手にゴックンできている。」ことができてきていれば、様子を見ながら2回食にすすめてみましょう。
中期(生後7から8か月ごろ)
1食分の食事量はどれくらい?
回答
5倍粥50~80g+野菜や果実20~30g+魚や肉15gくらいが1食の目安です。お粥とおかずをあわせて、子ども茶碗1杯位になります。個人差があるので、少食でも順調に発育していればOKです。
食事量が足りているか心配です。
回答
成長曲線のグラフに体重・身長を記入し、成長曲線のカーブに沿っているか確認しましょう。体重増加が見られなくなり、成長曲線から外れていく場合は医師に相談してその後の変化を観察しましょう。
(体重や身長の測定はアキシマエンシス(予約制)や商業施設のベビールームなどで測定できます。)
肉や魚を食べると、口からベーっとだします
回答
肉や魚は火を通すとパサパサになり口の中でまとまりにくく、赤ちゃんにとって飲み込みづらくなるものが多いです。水分を多めに滑らかに調理したり、とろみをつける・お粥に混ぜるなど口当たりをよくしてみましょう。
食べすぎが心配です
回答
離乳食を「口をモグモグ動かしてたべているか」をみてください。口をほとんど動かさず、丸呑みをしているようだったら、やわらかすぎたり固すぎるかもしれません。形状があっているか確認しましょう。舌でつぶせるくらい(大人の小指と親指で挟んでつぶれるくらい)が目安です。
野菜を食べません
回答
野菜は酸味や苦味を強く感じるものが多く苦手な味です。
離乳食を楽しく食べる体験を繰り返すことで好きな味になっていきます。赤ちゃんが口から出しても、あきらめず何度もチャレンジしましょう。
食べむらがあります
回答
知能が発達してくると、様々なことに興味が出てきて食事中に気が散ることがあります。昨日は食べたのに、今日はまったく食べないといったこともでてきます。
食べないからといって、必要以上に母乳やミルクを与えたり好きなものだけを与えたりするとリズムが崩れてしまいます。食事の時間帯はなるべく一定にし、食生活のリズムを乱さないようにすることが大切です。
後期(生後9から11か月ごろ)
食後のミルクをほしがらなくなりました
回答
離乳食をしっかり食べて、食後のミルクがいらない赤ちゃんもいます。食後に飲まなくても大丈夫ですが、1歳ごろまでは離乳食だけでは必要な栄養が摂りきれないので食後以外のタイミングで飲ませてあげてください(目安はミルクだと1日400ml)また、離乳食の食材としてミルクを使ってみましょう。
フォローアップミルクは飲んだほうがいいですか?
回答
フォローアップミルクは、母乳代替食品ではないので離乳食が順調に進んでいる場合は飲まなくてもかまいません。離乳食が十分に食べられているなら、今までどおり普通のミルクでかまいません。鉄分の不足が心配なときに離乳食の食材として使うこともお勧めです。
手づかみ食べは必要ですか?
回答
食べ物を触ったり握ったりすることで、食べ物への関心につながり自分で食べようという行動につながります。また、お皿の食べ物を見つけて手でつかみ、口に入れるという、目・手・口の協調動作を育てるためぜひ実施していただきたいです。
手づかみ食べをしません
回答
手が汚れるのを嫌がる子どももいます。こまめに手を拭けるように手拭を用意し、手の汚れにくい茹で野菜や細長く切った食パンなどを用意してみましょう。
好き嫌いがでてきました
回答
体調や気分によって、急に食べなくなったり別の食べ物を欲しがったりすることがあります。すんなり食べなくても「苦手な食材」と決めつけずに、固さや味付けを変えてチャレンジしていきましょう。
食事中に立ち上がったり、机に登ったりと落ち着いて食べません
回答
「いただきます」「ごちそうさま」と挨拶を習慣にして区切りをつけましょう。また、おもちゃを片付け、テレビを消して、食事に集中できるようにしましょう。
立ち上がって逃げ出したときも、追いかけて食べさせないでください。食事が遊びの一環になってしまいます。
完了期(生後12から18か月ごろ)
ミルクや母乳はどのように減らしていけば良いですか
回答
1歳ごろを目安に、離乳食の後のおっぱいやミルクをやめて食事でおなかを満たしていきます。また、1歳2~3ヶ月ごろに、食事と食事の間に飲んでいたおっぱいやミルクを牛乳やおやつに変え、入浴後や夜中に飲んでいたおっぱいやミルクは麦茶や白湯に置き換えて徐々に量を減らしていきましょう。
子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健係(アキシマ
エンシス校舎棟3階)
郵便番号:196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号:042-519-6006
ファックス番号:042-519-2803