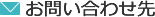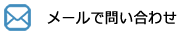食品ロスとは
更新日:2025年9月19日
食品ロスとはまだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことです。食品ロスは、資源の無駄遣いだけでなく、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出にもつながる深刻な問題です。
日本の食品ロス量(令和5年度推計)
日本では、年間で約464万トンもの食品ロスが発生しています(農林水産省及び環境省推計)。これを国民1人当たりにすると、1日102g(茶碗約1杯のご飯の量に相当)、年間約37キログラムの食品を捨てていることになります。
食品ロスは大きく、各家庭から発生する「家庭系食品ロス」と事業活動から発生する「事業系食品ロス」の2つに分けられます。464万トンのうち「家庭系食品ロス」が233万トン、「事業系食品ロス」が231万トンとなっています。
食品ロス削減のためにできることから始めよう!
食品ロス削減のためには、この問題を「他人事」ではなく「我が事」としてとらえ、「理解」するだけではなく日々の生活の中でできることを一人一人が考え「行動」に移すことが求められます。具体的には以下のとおりです。
買い物の際
- 買い物前に家にある食材をチェックし、期限表示を理解のうえ、使用時期を考慮し、てまえどり、見切り品等を活用する。
- 必要な食材をこまめに購入する。
- 空腹状態で買い物に行かない。
食品保存の際
- 食材に応じた適切な保存を行う。
- 冷蔵庫内の在庫管理を定期的に行う。
- 賞味期限を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないので、食べられるかどうか個別に判断する。
- 災害等に備え、家庭において食品を備蓄する場合には、普段から食品を少し多めに買い置きしておき、古いものから消費し、消費した分を買い足すことにより、食品の備蓄ができるローリングストック法を実践する。
ローリングストックについて詳しく見る(外部サイトにリンクします)。 - 家庭で余っている未開封の未利用食品は、近隣でシェアしたり、フードドライブを通じて寄付したりする。
調理の際
- 余った食材を鍋物や汁物に活用するなど、家にある食材を計画的に使い切る。
- 食材の食べきれる部分はできる限り無駄にしないようにする。
- 食べきれる量を調理し、食べきれなかったものについてリメイクなどの工夫をする。
外食の際
- 食べきれる量を注文し、提供された料理を食べきるようにする。
- 宴会時には最初と最後に料理を楽しむ時間を設ける3010運動を実践する。
- 料理が残った場合は自己責任の範囲で持ち帰る。
環境部 ごみ対策課 ごみ減量係
郵便番号:196-0001 昭島市美堀町3-8-1
電話番号:042-546-5300
ファックス番号:042-546-5900